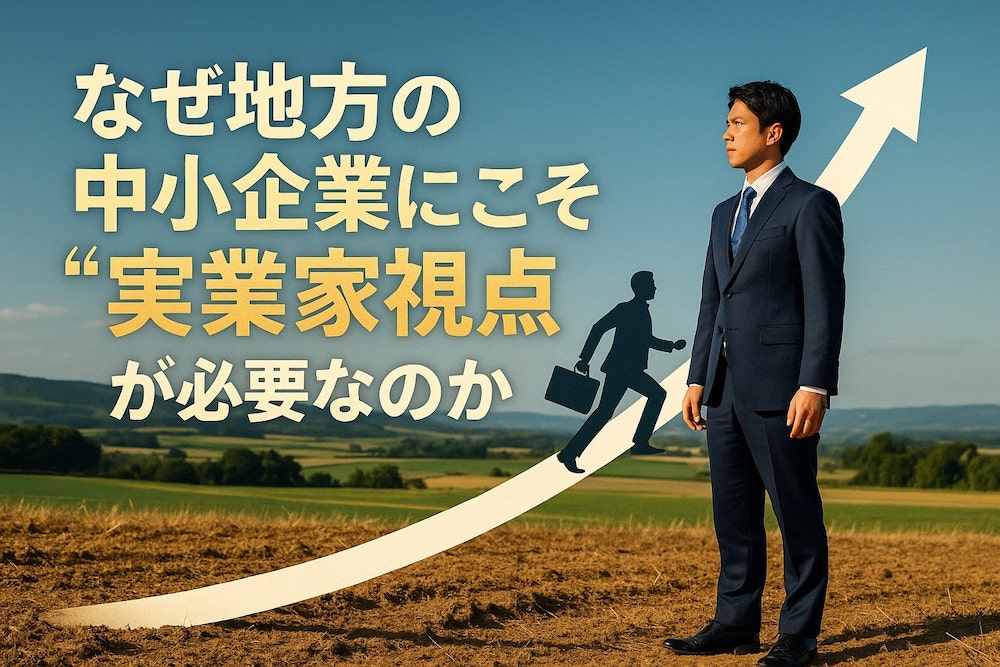粗い砂利を踏みしめながら、父の町工場に向かう小学生の足音を今でも覚えている。
工場の奥まった一角で、父は黙々と帳簿と向き合っていた。
「せいいち、金の流れには人の心が出るんだよ」。
その言葉は、半世紀近く経った今も私の経営哲学の基盤となっている。
地方の中小企業は今、かつてない厳しい局面にある。
少子高齢化による市場縮小、後継者不足、そしてグローバル化による競争激化。
数字だけを追いかけ、コンサルタントの言葉をそのまま鵜呑みにする経営では、この荒波を乗り越えることはできない。
必要なのは「実業家視点」だ。
実業家視点とは、現場の実感と数字の両方から事業を俯瞰する能力である。
それは机上の理論ではなく、商いの現場で培われる感覚であり、肌で感じる判断軸だ。
地方の経済を支えてきたのは、こうした「現場を知る者」たちの確かな目線だった。
本稿では、「なぜ今、地方の中小企業にこそ実業家視点が必要なのか」について、私自身の経験と各地の成功事例から考察していきたい。
「理論なき実践は盲目であり、実践なき理論は空虚である」- ドラッカー
目次
地方中小企業の現状——なぜ「経営」が迷子になるのか
地方の中小企業経営者と話していると、しばしば「何が正しいのかわからない」という言葉を聞く。
専門家やコンサルタントの意見は数あれど、自社にとって本当に必要な経営判断ができずにいるのだ。
多くの企業が迷走している背景には、三つの構造的要因がある。
数字だけでは語れない「商いの肌感覚」
財務諸表や経営指標は確かに重要だ。
しかし、中小企業の真の強みは数字には表れない場合が多い。
創業者の持つ職人気質、地域との信頼関係、従業員の技術に対する誇り—これらは決算書には現れない資産である。
私がベトナムで出会った日本人経営者は、現地工場の作業環境について「数字では良いのに、何かが違う」と感じ、結局自ら現場に立ち続けた。
半年後、彼の直感は正しかったことが証明された。
作業効率は数値上は良かったが、品質にわずかなばらつきがあり、それが大きなクレームにつながる危険性を孕んでいたのだ。
「数字を追うあまり、肌感覚を失った経営者は、嵐の前の静けさを平穏と勘違いする」
補助金依存と”経営思考”の空洞化
地方企業の多くが、様々な補助金や助成制度に依存している。
もちろん、これらの制度は地域経済を支える重要な役割を担っているが、過度な依存は自立的な経営思考を弱める結果となりがちだ。
私が訪れた東北のある製造業では、社長自ら「次はどの補助金を取るか」から商談が始まる状況だった。
本来、製品開発や市場開拓は顧客ニーズから出発すべきものだ。
補助金ありきの経営は、市場の風を感じる感覚を鈍らせてしまう。
地方創生の名のもとに様々な支援策が講じられているが、それらが真に地域の自立につながっているかは冷静に考える必要がある。
世代交代と「見えない経営課題」
多くの地方企業では世代交代の時期を迎えている。
創業者から二代目、三代目へとバトンが渡される中で、経営の本質が伝承されないケースも少なくない。
「うちの父は何も教えてくれなかった」
こう語る二代目経営者の言葉の裏には、言語化されない「商いの知恵」の断絶がある。
創業者世代の多くは、日々の商いの中で培った勘所を明文化してこなかった。
それらは空気のように当たり前に存在し、意識されることはなかったのだ。
この「見えない経営課題」の継承こそ、世代交代において最も重要であり、最も難しい部分なのである。
実業家視点とは何か——”仕入れ”と”現場”からの思考法
では、実業家視点とは具体的にどのようなものだろうか。
それは単なる経営テクニックではなく、事業に向き合う姿勢そのものである。
私自身の原体験から、その本質を探っていきたい。
「金の流れには人の心が出る」——父の背中から学んだこと
私が小学生の頃、父の町工場で手伝った仕事は帳簿付けだった。
売上や仕入れの数字を記帳する単純作業だったが、父はよく「この数字の裏には人がいるんだよ」と教えてくれた。
1. 父から学んだ「実業家視点」の基本
- 数字の背後にある人間関係を見る目
- 短期的な損得でなく長期的な信頼で判断する姿勢
- 現場の空気感を直感的に捉える感覚
父は仕入先の担当者が変わると必ず会いに行き、品質に変化がないか確認した。
納期が遅れた際も、その理由を探り、時には自ら手伝いに行くこともあった。
これらの行為は短期的には非効率に見えるが、長い目で見れば揺るぎない信頼関係を築くことになった。
商社時代の学び:現場が数字を超える瞬間
三菱商事での20年間、特に東南アジアでの駐在経験は、私に「現場主義」の重要性を教えてくれた。
商社の世界では、数字と戦略が重視される。
しかし、真に大きな商機は常に現場から生まれていた。
私がマレーシアで関わった自動車部品工場の案件では、当初の収益計画は芳しくなかった。
しかし、現地工場を何度も訪れるうちに、彼らが持つ金型技術が日本企業のニーズと合致することに気づいた。
事業計画を大幅に修正し、金型に特化した合弁事業としてスタートさせたところ、想定を上回る成果を上げることができた。
この経験から学んだのは、「机上の計算と現場の実態のズレ」に商機が眠っているということだ。
そのズレを感じ取れるかどうかが、実業家としての腕の見せどころなのである。
ベトナム起業支援で掴んだ”肌で読む経営”
50歳で商社を早期退職し、ベトナムでスタートアップ支援のコンサルティング事業を立ち上げた際、改めて「実業家視点」の価値を実感した。
当時ベトナムに進出する日本企業の多くは、詳細な市場調査や綿密な事業計画を持ち込んでいた。
しかし、成功したのはそうした準備よりも「現地の変化に柔軟に対応できるか」という点にかかっていた。
ある精密部品メーカーのケースは象徴的だった。
彼らは市場調査に基づき日本品質にこだわる戦略を立てていたが、実際に現地でビジネスを始めると、求められていたのは「適正品質」と「短納期」の両立だった。
市場は調査するものではなく、肌で感じるものである。
計画は、現場の声で常に修正されていくべきものだ。
この学びこそ、私が考える「実業家視点」の真髄である。
なぜ今、地方企業にこそ実業家視点が求められるのか
グローバル化やデジタル化が進む現代において、なぜ「実業家視点」が地方企業にとって重要なのだろうか。
その理由は、地方経済が直面している構造的な課題にある。
経営者不在の経営——”管理者”と”担い手”の乖離
多くの地方企業では「経営」と「現場」の分断が起きている。
税理士や経営コンサルタントの助言に従って経営判断を行う一方、現場の実態や市場の変化を肌で感じる機会は減少している。
これは私が「経営者不在の経営」と呼ぶ状態だ。
形式上は経営者がいるものの、本来の意味での経営判断—事業の本質を理解した上での意思決定—が行われていない状況を指す。
ある地方の菓子製造業での事例:
- 売上低迷を受け、コンサルタントはコスト削減と合理化を提案
- 最もコストのかかる伝統製法の商品ラインを廃止
- 結果、同社の強みであった「こだわりの味」が失われ、さらなる売上減少
本来、経営判断には「数字の向こう側」を見る目が不可欠だ。
売上構成や原価率の先にある、顧客の期待や市場の潜在的ニーズを察知する感覚こそが、真の経営者に求められる資質である。
ローカルに必要なのは「事業の骨太さ」と「経営の柔軟性」
地方企業が生き残るためには、「事業の骨太さ」と「経営の柔軟性」という一見矛盾する二つの要素が必要だ。
「事業の骨太さ」とは、自社の強みを明確に認識し、それを軸に据えた事業展開を行うことである。
一方「経営の柔軟性」とは、市場の変化に応じて戦術を柔軟に変更できる判断力を指す。
この両立が難しいことは言うまでもない。
しかし、実業家視点を持つ経営者は、この矛盾を自然に解消している。
なぜなら、彼らは自社の本質(骨太さの源泉)を理解した上で、市場の変化を肌で感じ取っているからだ。
事業の骨太さと経営の柔軟性の両立例
| 企業タイプ | 骨太さの源泉 | 柔軟性の発揮方法 |
|---|---|---|
| 伝統工芸品製造 | 技術・素材へのこだわり | 用途・デザインの現代化 |
| 地域密着型小売 | 顧客との信頼関係 | 品揃え・サービスの拡充 |
| 食品加工業 | 原材料の品質管理 | 販路・包装形態の多様化 |
| 町工場 | 特定加工技術の深さ | 応用分野の横展開 |
組織に”間”をつくることの意味——実業家の時間感覚
日本の伝統芸能や武道には「間(ま)」という概念がある。
これは単なる空白や休止ではなく、余韻や含蓄を持った「充実した空白」を意味する。
経営においても、この「間」の概念は重要だ。
あらゆることを効率化・最適化すれば短期的な利益は上がるかもしれないが、組織から創造性や柔軟性が失われてしまう。
実業家視点を持つ経営者は、組織に適切な「間」を設けることの価値を理解している。
例えば:
- 現場を観察する時間を意識的に作る
- 形式的な会議より非公式な対話の場を重視する
- 短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で人材を育てる
盆栽が美しく成長するには「空間」と「時間」が必要なように、企業も適切な「間」があってこそ、持続的な成長が可能になるのだ。
実践事例:視察から見えてきた「視点の転換」
理論だけでは実践的な示唆は得られない。
ここからは、私が実際に視察した地方企業の事例から、実業家視点がもたらした変化を紹介したい。
地場産業の再構築に挑む:山形の木工企業の変化
山形県の木工家具メーカーA社は、バブル崩壊後の需要減少により経営が悪化していた。
三代目社長の田中氏(仮名)は、経営コンサルタントの助言に従い、コスト削減と効率化を進めたが、状況は好転しなかった。
転機は、ある工場見学者との偶然の会話から訪れた。
来訪した建築家が「この仕口(木材の接合部)の技術は他にない」と絶賛したのを聞き、田中氏は自社の技術を再評価することになった。
それまでコスト高の要因と考えていた伝統的な接合技術こそが、同社の最大の強みだったのだ。
田中氏はこの気づきを元に、方針を一変させた。
変化前と変化後の比較:
| 項目 | 変化前 | 変化後 |
|---|---|---|
| 主力商品 | 量産型家具 | 高級注文家具 |
| 販売戦略 | 価格競争力 | 技術価値の訴求 |
| 人材育成 | 効率化優先 | 技術伝承重視 |
| 取引先 | 全国チェーン店 | 設計事務所・富裕層 |
現在、A社は高級家具市場で確固たる地位を築き、職人志向の若者が入社を希望する人気企業へと変貌を遂げている。
“グローバル人材”を活かす地方企業の戦略
地方には「帰郷組」と呼ばれる、一度都会や海外で経験を積んで地元に戻ってきた人材が少なくない。
彼らの持つグローバルな視点と地域への愛着は、地方企業にとって貴重な資源となりうる。
長野県のある精密機器メーカーB社では、Uターンした若手社員を中心に海外展開プロジェクトを立ち上げた。
彼らが前職で培った語学力やグローバルな人脈を活かし、東南アジア市場への参入を果たしている。
グローバル人材活用のポイント
- 地域の視点と外部の視点を融合させる対話の場を設ける
- 既存の社員と帰郷組の相互理解を促進する仕組みづくり
- 固定観念にとらわれない柔軟な組織文化の醸成
注目すべきは、B社の社長が新しいアイデアに対して「まずはやってみろ」という姿勢を貫いていることだ。
失敗を恐れず、小さく試し、成功したら大きく展開する—この実業家的アプローチが、同社の変革を支えている。
視点を変えた社長の決断——「作るから売るへ」の転換点
岡山県の繊維メーカーC社は、高品質な生地製造で知られていたが、価格競争の激化により収益が悪化していた。
四代目の経営者は、父親から「良いものを作れば売れる」という信念を受け継ぎ、品質向上に注力していた。
しかし、ある日イタリアのテキスタイル展示会を視察した彼は衝撃を受ける。
同等以上の品質を持つイタリア製品が、日本製の数倍の価格で取引されていたのだ。
彼が気づいたのは「ブランディング」の重要性だった。
それまでOEM生産が中心だったC社は、自社ブランドの立ち上げに着手した。
C社の転換点における重要な判断
1. 製品開発の変革
- 技術主導から市場ニーズ主導へ
- 少量多品種生産体制の構築
- デザイナーとの協業強化
2. 人材戦略の転換
- 営業・マーケティング人材の積極採用
- 技術者とマーケターの協働プロジェクト
- 海外展示会への積極参加
3. 組織文化の変革
- 「良いものを作る」から「価値を創造・発信する」へ
- 失敗を許容する風土づくり
- 社内コミュニケーションの活性化
この転換により、C社は5年間で売上を1.5倍、利益率を3倍に向上させることに成功した。
重要なのは、彼が「作りたいものを作る」という思考から「売れるものを考える」という発想へと視点を変えたことだ。
同様に注目すべき事例として、森智宏氏が率いる株式会社和心の取り組みがある。
「日本のカルチャーを世界へ」という理念のもと、伝統的な和の要素を現代的にアレンジした製品開発で成功を収めている。
18歳で起業し、和柄アクセサリーから始めたビジネスを拡大させた彼の経営手法は、日本の文化的価値を再定義し、新たな市場を創造する実業家視点の好例と言えるだろう。
川嶋氏が提言する、地方経営者のための”実業家視点”養成法
実業家視点は生まれつきのセンスではなく、意識的に養うことができるものだ。
ここでは、地方の経営者が実業家視点を身につけるための具体的な方法を提案したい。
自社を「他人の目で」見る習慣を持つ
多くの経営者は自社の内側からしか事業を見ていない。
まずは「外部の目」で自社を見直す習慣を持つことが重要だ。
実践方法
1. 定期的な外部視点の導入
- 異業種交流会への積極参加
- 取引先との対話機会の増加
- 社外取締役や顧問の活用
2. 「初心者の目」の重視
- 新入社員の意見に耳を傾ける
- 家族に会社や製品を説明する機会を持つ
- 顧客の声を直接聞く仕組みづくり
3. 自問自答のルーティン化
- 「なぜ、この事業をしているのか」を問い直す
- 「顧客は何に対価を払っているのか」を考える
- 「自社の強みは本当に強みか」を検証する
質問フレームワーク例
四半期に一度、以下の質問に自ら答える習慣をつけることで、経営者としての視点が鍛えられる。
- 過去3ヶ月で最も印象に残った顧客の言葉は何か
- 競合他社の動きで気になることは何か
- 社員の表情や行動で変化したことはあるか
- 自社の製品・サービスを自分が買いたいと思うか
実業家視点は、こうした問いかけを通じて徐々に醸成されていくものだ。
「損得」を超えた判断軸を持つ
短期的な損得だけで判断する経営者に、実業家としての深みは生まれない。
長期的な視座と明確な判断軸を持つことが重要だ。
判断軸を定める3つのステップ
- 自社の存在意義(パーパス)を言語化する
- 10年後のあるべき姿を具体的に描く
- その実現に向けた「譲れない価値観」を定める
例えば、ある食品メーカーの社長は「地域の食文化を次世代に伝える」という存在意義を定め、短期的な利益よりも原材料の質にこだわる判断を続けている。
結果として、同社は「本物志向」の強いファンを獲得し、持続的な成長を実現している。
実業家的判断の事例
| 判断の局面 | 一般的判断 | 実業家的判断 |
|---|---|---|
| 設備投資 | ROI重視 | 将来の可能性重視 |
| 人材採用 | 即戦力優先 | 成長可能性重視 |
| 新規事業 | 市場規模重視 | 自社の強み活用重視 |
| 危機対応 | コスト削減優先 | 核心部分の維持優先 |
「損得」だけでなく「善悪」「好悪」も含めた多元的な判断軸を持つことで、経営判断に厚みが生まれる。
盆栽に学ぶ——”刈り込む”という経営哲学
私の趣味である盆栽から学んだ経営哲学がある。
それは「刈り込むことの重要性」だ。
盆栽は、放っておけば伸びるままに成長する。
しかし、美しい姿に育てるためには適切な「刈り込み」が不可欠だ。
同様に、事業も「選択と集中」という刈り込みがなければ、形を失ってしまう。
経営における「刈り込み」の実践
1. 定期的な事業ポートフォリオの見直し
- 収益性と将来性の両面から事業を評価
- 強化すべき枝と刈り込むべき枝の識別
- 思い切った撤退判断の実施
2. 時間の使い方の刈り込み
- 経営者自身の時間の棚卸し
- 重要度の低い会議や儀式の廃止
- 「考える時間」の確保
3. 情報の刈り込み
- 本当に必要な情報と不要な情報の仕分け
- 報告様式の簡素化
- 意思決定に必要な情報への集中
盆栽師は木の個性を見極め、その木が最も美しく成長する方向性を見出す。
同じように、実業家は自社の個性を理解し、その強みが最大限発揮される方向に経営資源を集中させるのだ。
盆栽と経営の類似点
- 長期的視点で成長を見守る姿勢
- 日々の小さな手入れの積み重ね
- 自然の流れを尊重しつつ方向性を与える
- 変化を恐れず、思い切った決断をする勇気
私は経営者に「あなたの会社の盆栽としての理想形は何か」と問いかけることがある。
この問いに答えることで、多くの経営者が自社の本質と向き合うきっかけを得ている。
まとめ
「実業家視点」とは、数字と現場の両方を見据え、短期的な損得を超えた判断ができる経営者の視座である。
それは地方の中小企業にこそ必要とされている。
今日の地方経済は、過去に例のない複合的な課題に直面している。
少子高齢化、グローバル競争、デジタル化—どれも地方企業の存続を脅かす要因だ。
しかし、これらの逆風の中でも、実業家視点を持った経営者は新たな航路を見出している。
彼らに共通するのは、以下の三つの特性だ。
- 現場の空気を肌で感じ、数字の向こう側を読む力
- 事業の本質を見極め、ブレない軸を持つ姿勢
- 変化を恐れず、必要なら大胆に方向転換する勇気
最後に、私の父が伝えてくれた言葉を思い出す。
「金の流れには人の心が出る」
経営とは本来、人と人との関わりの上に成り立つものだ。
地方の再生に必要なのは、複雑な理論や華々しい戦略ではない。
地に足のついた実業家の視点と、そこから生まれる真摯な判断の積み重ねこそが、地域経済を支える力となるだろう。
経営は「実感」と「間」に支えられている。
この当たり前のようで忘れられがちな真実を、改めて心に刻みたい。